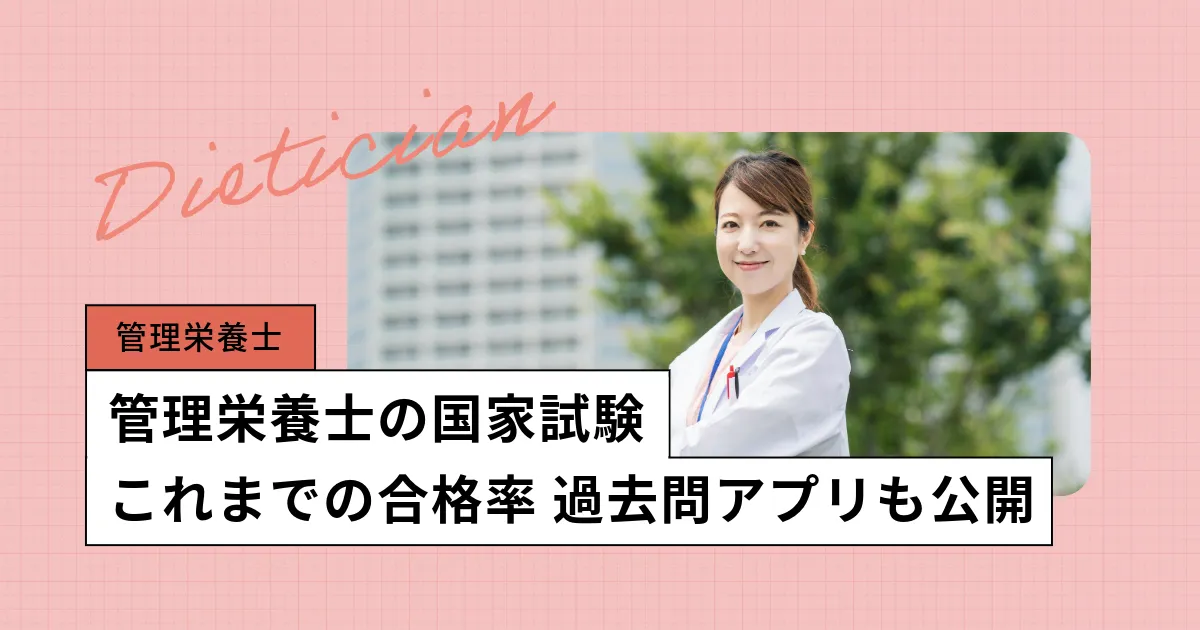管理栄養士にしかできないことは?
管理栄養士は、現在どのような立場でその専門性が必要とされているのでしょうか。
病院勤務の管理栄養士を例にすると、10年前は給食の栄養管理が主な役割でした。しかし現在は、病棟への管理栄養士の配置が義務付けられ、入院や外来の患者さんの栄養管理をする割合が増えています。この背景には、管理栄養士を含む医療従事者による栄養管理が、治療への効果につながっている事実があります。
今後さらに活躍が期待される、管理栄養士に特化した業務や必要とされる場所について解説します。
目次
管理栄養士にしかできないこと
管理栄養士は国家資格で「栄養や食生活の面から健康の維持・増進と疾病の予防・治療等を推進する専門家」です。管理栄養士に特化してできる業務・活躍の分野をいくつか紹介します。
病院で栄養管理・指導:入院、外来、在宅
現在、入院患者さんを受け入れる特定の病院では、管理栄養士の1名以上の配置が義務づけられています。
患者さんに対して、医師の指導のもと一般食の内容や形態を決定でき、また栄養指導では時期の判断や実施ができます。特別治療食については医師に内容や形態の提案を行うことができます。管理栄養士の配置は、「入院基本料・特定入院料の施設基準」を加算する病院の要件となっています。
栄養管理が評価されている理由は?
管理栄養士数に比例して入院日数が短縮
ある調査では、管理栄養士の配置人数が入院患者に対して多いほど、退院までの日数が短縮できるという結果となりました。また術後の経口摂取再開までの日数が短いほど、在院日数が短いという評価もあります。ケガなど術後すぐに経口摂取の開始が可能な手術においても、適切な栄養管理を実施することで術後の合併症発生率や死亡率が有意に低下することがあきらかになっています。
栄養関係の加算、取り組み(令和6年診療報酬改定)
上記のような早期からの栄養管理、入院、外来、在宅での栄養管理が評価されています。
令和6年診療報酬改定では、栄養関係の報酬が複数新設されました。入院前から入院中、外来、在宅の各フェーズで、栄養管理の重要性は増し、管理栄養士の活躍の場はますます広がっています。
入院
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(新設)、経腸栄養管理加算(新設)、栄養情報連携料の新設、小児個別栄養食事管理加算(新設)、入院基本料等の見直し(栄養管理体制の基準の明確化)、入院時支援加算の見直し、入院時食事療養費の見直し、回復期リハビリテーション病棟入院料1の見直し(GLIM基準を要件化)
外来
生活習慣病に係る医学管理料の見直し、慢性腎臓病透析予防指導管理料(新設)
在宅
在宅療養支援診療所・病院における訪問栄養食事指導の推進、介護障害連携加算の算定要件に訪問栄養食事指導に関する実績
特定給食施設での栄養管理
管理栄養士が必置の施設があります
給食施設の中でも、管理栄養士の設置を義務づけている施設があります。
医療的、または特別な栄養管理を必要とされる「特定給食施設」では、管理栄養士の配置が義務づけられています。
このような役割も管理栄養士にしかできないことです。
具体的な施設の種類は、病院、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉施設、乳児院、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設などがあります。
学会等での論文発表
上記のように入院前から在宅まであらゆる場所で栄養管理が重視されています。栄養管理の経験や実績を論文としてまとめ、医療や健康増進に貢献することは管理栄養士にしかできない役割です。
管理栄養士資格がベースとなる資格の取得
管理栄養士が受験資格となる上位の資格があります。
認定管理栄養士認定制度や特定分野別認定制度、専門分野別認定制度といった認定制度の仕組みがあり、専門性を高めることでさらなるキャリアアップも望めます。
管理栄養士の仕事は、対象となる方の病状や生活習慣、食の好みなどに応じて個別に対応していく必要があり、そのためには病気や栄養に関する最新情報も常に取り入れていく必要があります。そのように継続したスキルアップが大切な職業であり、さらに管理栄養士の専門性を高めることにつながります。
管理栄養士と栄養士の違い
「栄養士」も管理栄養士と同様に食と栄養を支える専門家です。主に健康な人を対象にしているのが管理栄養士と異なる点です。
管理栄養士は、健康な方だけでなく、「医学的な管理が必要な傷病者」に対しても個別の栄養管理や食事指導を行う知識や技術があると認められています。
💡 POINT
・管理栄養士は病気の人の栄養管理も行う
・栄養士は主に健康な人を管理
管理栄養士の専門性とは
管理栄養士には、食と栄養の面から健康を支える専門家としての役割があります。どのような業務が管理栄養士に認められているのかを説明します。
特定の医療行為への関与
管理栄養士は、病院やクリニックなどの医療機関で、個々の患者さんに合わせて食事療法を提供することができます。病状に合わせた献立の作成や、食事量の調査や面談による栄養状態の把握・食事指導、医師や看護師などと連携した栄養療法の実施が可能です。外来患者さんや在宅患者さんへのアドバイスや食事指導なども管理栄養士の大切な役割です。
栄養管理の立案と実施
管理栄養士の役割の一つに、集団または個人に対する栄養管理があります。医療機関や福祉施設、教育施設などで、病状や年齢などによって異なる、特定の栄養状態に合わせた食事計画の立案と実施を行います。また、対象の人に応じた献立の作成や調理方法の指導もすることができます。
栄養ケア・マネジメント
栄養管理計画の見直しやモニタリングを実施し、より効果的な食生活改善を支援するのも管理栄養士の大切な役割です。栄養管理には「栄養管理プロセス」と呼ばれる国際的な基準があり、「栄養アセスメント(栄養状態の評価」)「栄養診断(栄養状態の判定)」「栄養介入(計画と実施)」「栄養モニタリングと評価」の4段階で進めることで、プロセスの標準化による展開や共有、栄養問題の理解の容易化を図ることができます。
栄養指導および教育活動
管理栄養士は、疾病予防や健康増進を目的とした栄養教育活動をすることができます。地域自治体や企業が主催する健康セミナーでの講演、食事や栄養に関する相談会の実施、料理教室の開催といった取り組みを通じて、地域の方々の食と栄養に関する意識を高めていくことが求められています。
管理栄養士に期待される分野
食生活の改善が重要視されるようになり、管理栄養士の活躍場所は年々広がりを見せています。その中でも代表的な活躍場所が、医療機関や福祉施設です。入院患者さんや外来患者さんへの栄養指導や栄養管理、入所・通所しているご高齢者や乳幼児に向けた献立の作成などを通して健康管理を行っています。
低栄養傾向の高齢者のケア
低栄養傾向の高齢者を減らすことが重要な目標となっています。下のグラフは、BMI20以下となる、低栄養傾向のある高齢者の割合を示したもの。高齢男性で12.4%、高齢女性で20.7%、年齢が上がるにつれて割合が高くなります。低栄養状態は「フレイル」につながり、さらに筋肉量が減って歩行や日常生活に支障をきたすと、要介護状態となってしまう。肥満よりもやせの方が死亡率が高いという研究結果もあり、低栄養の高齢者を減らすことが大きな課題となっています。
低栄養を防ぐためには、早期に管理栄養士が介入し、食事や栄養摂取の状態を確認し、改善を促すことが大切です。介護が必要になる前に介入するために、まだ介護を受けていない人と接する薬局や行政機関などに在籍す る管理栄養士が、低栄養状態に気づき、対処する効果が期待されています。
管理栄養士が行う在宅訪問
在宅療養をしている人に対する栄養指導では、現在の栄養・食事状況の確認、献立の提案、家族への料理指導など、個々に合わせた支援をします。
在宅訪問は、医療保険では「在宅患者訪問栄養食事指導」、介護保険では「居宅療養管理指導」として行われます。主治医の指示のもと、勤め先の医療機関の患者さん宅に行くほか、地域の他の医療機関、介護事業所等から依頼される場合もあります。
低栄養やフレイルが広く課題となる中、その予防や改善のほか、慢性生活習慣病の管理、摂食嚥下障害の人への支援がよくある事例です。支援内容としては、体重や栄養状態、現在の食事の状況を把握した上でのメニューや食べやすい方法などを考案すること。家族やヘルパーに調理の指導をすることもあり、また、介護や医療チームとの情報共有、連携も必要となります。
このことから、食と栄養の観点から健康をサポートする管理栄養士の需要は、さらに拡大していくと考えられます。管理栄養士になるメリットという点からみれば、安定した需要が見込めること、ご高齢者や子どもを中心に多くの人々の健康をサポートでき、社会的貢献が可能な職業であることが、大きなメリットといえるでしょう。
管理栄養士の今後の可能性
働き方が多様になりつつある現代において、管理栄養士もその例外ではありません。近年では、特定の医療機関や企業、施設に所属せず、フリーランスとして活躍している管理栄養士も増えてきています。その仕事内容も、栄養・食育に関するオンラインセミナーの開催、アスリートなどの個人に対する専属栄養指導、食品メーカーや健康・美容メディアへのレシピ提供など、多種多様です。
働く場所に関しても、フィットネスジムで体作りに最適な食事メニューを指導したり、歯科医院でお口の健康や摂食・嚥下機能を考慮した献立提案をしたりと広がりを見せています。オンラインでのカウンセリングやセミナーが一般的になったことで、国内のみならず海外に住む方への食育活動や栄養指導も簡単にできるようになったため、管理栄養士の活躍場所は今後さらに広がっていくと考えられます。
まとめ
管理栄養士は、食事と栄養のプロフェッショナルとして人々の健康を支えることができる職業です。食の欧米化や生活習慣病の増加、少子高齢化が進むこれからの社会において、その重要性やニーズはさらに高まっていくでしょう。管理栄養士を目指し勉強をしている方、管理栄養士としてさらなるキャリアアップを目指している方は、そういった社会やニーズの変化を捉えながら自分に合った管理栄養士としての働き方を見つけていっていただければと思います。