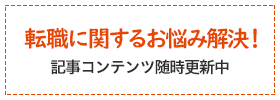.png?fm=webp&fit=crop&w=680&h=357)
「基本給が低いと損をするかも」と聞いても特にピンとこないかもしれません。転職中は給料の総額に意識が向きがちです。今回は雇用契約書などに書かれている「基本給」について転職前に知っておきたいポイントをまとめました。
基本給とは何か?
基本給は給与の基準となるものですが、手取り額や総支給額とは異なるため、あまり気にしていない方も多いのではないでしょうか。まずは、基本給の基本的な知識について解説します。
基本給の定義
基本給とは、給与のベースとなる基本賃金のことです。一定期間働けば毎月固定で支給される賃金のことであり、残業手当や役職手当、インセンティブといった各種手当は含まれていません。「本給」と呼ばれることもあります。
基本給と月収・手取り・固定給との違い
月収とは、基本給に固定手当や変動手当などを加えた総支給額のことです。「額面給与」「額面」「給与」などと呼ばれることもあります。そして、この月収から社会保険料や税金などを差し引いて、実際に受け取ることのできる額が「手取り」です。一般的に手取りは、月収(額面給与)の7~8割となっています。
固定給は、基本給に役職手当や住宅手当などの「固定手当」を足した額を指し、「月給」と呼ばれることもあります。残業手当やインセンティブなどは毎月額が変動する「変動手当」であり、固定給の内訳には基本的に含まれません。ただし、残業代は、固定残業代(みなし残業代)として基本給の中に組み込まれている場合や、固定手当に含まれている場合もあります。
主な基本給の決め方
企業によって基本給の決め方は異なります。代表的な3つの決め方について解説します。
仕事給
仕事給は、職務の性質によって基本給の額を決める方法です。仕事の内容や業務範囲、専門性の高さ、責任範囲、成果、職務遂行能力などが重視される方式であり、学歴や年齢、勤務年数などは加味されません。欧米で多く採用されている方式であり、主に成果主義型の企業で取り入れられています。
属人給
属人給は、属人的な要素で基本給の額を決める方法です。学歴や年齢、勤続年数などで基本給が決定する方式であり、年功序列型の給与体系も属人給に含まれます。仕事の成果が基本給に反映されない反面、安定的な収入と昇給が見込める方式です。
総合給
総合給は、仕事給と属人給を組み合わせて基本給の額を決める方法です。学歴や年齢、勤続年数といった属人的要素をベースに、仕事の内容や成果を加味して基本給を決定する方式であり、日本の多くの企業がこの総合給方式を取り入れています。
基本給が低いと損をする理由
就職・転職活動をする際などに、額面給与や手取り額は気にしても、基本給はあまり気にしないという方も多いかもしれません。しかし、基本給が低いと損をする可能性があります。基本給が与える影響について解説します。
時間外手当への影響
法定労働時間を超えて働いたり、深夜や法定休日に勤務した場合、残業代や深夜手当、休日出勤手当が支給されます。これらの時間外手当は「1時間あたりの基礎賃金×労働時間×割増率」という計算式で算出されており、「基礎賃金」とは家族手当や通勤手当など特定の手当てを除く諸手当と基本給を足した金額のことです。そのため、基本給の額が低ければその分時間外手当も少なくなります。
ボーナスや退職金への影響
ボーナス(賞与)や退職金は支給が義務付けられているものではなく、その算出方法も企業によってさまざまです。しかし、多くの企業では基本給をもとに計算していることが多いため、基本給が少ないとボーナスや退職金の額も比例して少なくなることがほとんどです。
例えば、額面給与が30万円と同額だったとしても、基本給が20万円であれば3か月分の賞与は60万円、基本給が25万円であれば75万円と、15万円もの差がついてしまいます。
求人情報に「ボーナス〇か月分」と記載があり、その要素にメリットを感じるのであれば、何の金額の3か月分かをしっかりと確認する必要があります。
手当やボーナスがカットされた場合の影響
基本給は労働基準法により補償されており、労働者の同意を得ずに減額やカットを行うことはできません。それに対し各種手当やボーナスは、企業の業績や方針転換によって差し止めや減額をすることが可能です。もし各種手当やボーナスの支給が廃止された場合、基本給が低ければ手取り額が大幅に減額され、大きなダメージを負うことになります。
💡基本給が低いと損をする理由
- 基本給を含む基礎賃金は残業代のベースになる
- ボーナス・退職金のベースになる
- 給与がマイナスになった場合の影響
基本給を上げるための交渉術
基本給は各種手当のように簡単に減額やカットができないため、企業側からするとそう単純に上げられるものではありません。では、そのような状況の中で基本給を上げたい場合、どのように交渉すればいいのでしょうか。現職での基本給交渉のポイントと、転職活動時の基本給交渉のポイントを解説します。
現職での基本給交渉のタイミングと準備
基本給交渉においてまず覚えておきたいのは、交渉の内容やタイミングがとても重要だということです。給与交渉自体は悪いことではありませんが、伝え方を間違ってしまえば、自分の印象を悪くしかねません。会社の業績や自身の仕事内容などを総合的に見ながら交渉を行うようにしましょう。
基本給交渉のタイミングとして適しているのは、業務において大きな成果を上げた後や専門資格を取得した際、担当業務や部下が増えた際などです。会社への貢献度の高さや、会社に必要とされる人材であることをアピールできるタイミングであれば、交渉が有利に進みやすくなります。
交渉の事前準備としては、同じ業界や地域での給与相場を調べたり、会社の経営状態を把握しておいたりすることが大切です。優れた成果を上げた直後であっても、相場からかけ離れた額の交渉や、会社全体の業績が伸び悩んでいるタイミングでは、失敗する可能性が高くなります。そのほか、交渉の材料となる自身の業務量や実績に関するデータも用意しておきましょう。
そして実際の交渉の場では、会社や上司への感謝、今後どのように会社に貢献していきたいと思っているかなどを交えて交渉を行うのがおすすめです。「自分のことだけを考えている」と思われないようにすることで、成功率が高くなります。
転職活動時の基本給交渉のポイント
転職活動時に希望年収を聞かれた際や、提示された基本給や各種手当が自分の能力に見合っていないと感じる場合には、交渉を行うことができます。ただし、現職での基本給交渉時と同様に、給与交渉にはリスクも伴います。「尊大な人間だ」「自分の能力を過大評価している」と捉えられないよう、謙虚な姿勢で相談しましょう。
転職活動時に交渉をする際のタイミングとしては、希望年収を聞かれた際がベストです。もしそういった待遇・報酬面についての話が出なかった場合には、面接終盤に質問事項がないか聞かれた際に確認しましょう。ただし、真っ先に給与について聞いてしまうと印象が悪くなる可能性があります。キャリアビジョンなど、そのほかのことについて聞いてから給与について確認するのがおすすめです。
求人票で確認するべき給与・待遇
労働条件通知書が提示されてから給与交渉をするのは簡単なことではありません。リスクも伴うため、転職活動をする際は応募前にしっかりと求人票を確認しておくようにしましょう。
基本給と各種手当
総支給額(月収・額面給与)だけでなく、その内訳も細かく確認しておくことが大切です。基本給はいくらなのか、残業代は固定制(みなし残業)なのかそうではないのか、各種手当にはどのようなものがありそれぞれいくらなのかといったことをきちんと確認しておきましょう。
給与の幅や上限
「22万円~27万円」などのように、給与の額に幅や上限が設けられていることがあります。これは、求職者の経験やスキルに応じて給与額が決定されることを意味します。多くの場合は、一次面接後には給与が決まりますので、二次面接や内定後面談の際に確認しましょう。
覚えておきたい主な支給・控除項目
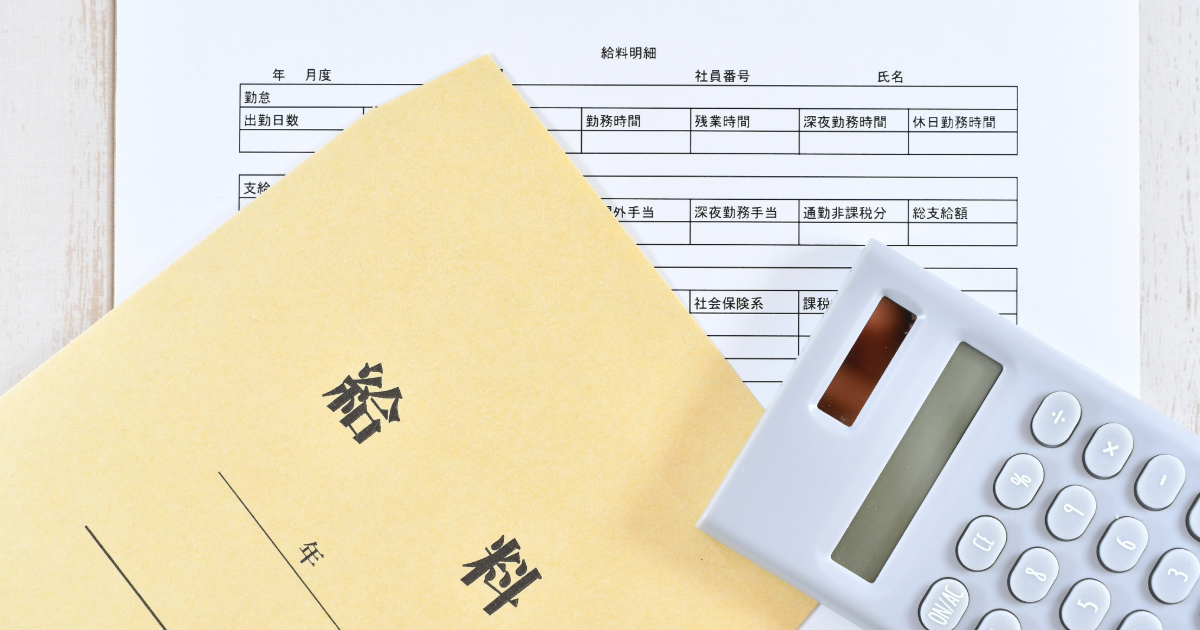
基本給に各種手当を足し、そこから社会保険料や税金を差し引いた額が、最終的に受け取ることができる手取り額です。主な支給項目、控除項目について解説します。
残業手当
残業手当は、所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる割増賃金のことです。労働基準法で定められた労働時間内に収まるものの企業で定めた規定を超えた場合を法定内残業、労働基準法で定められている「1日8時間」「1週間で40時間」を超えた場合を法定外残業といい、法定外残業に対しては割増率は1.25倍と定められています。
休日手当
休日手当は、休日出勤をした際に支払われる手当です。1週間に1日の休日、または4週間に4日以上の休日が労働基準法により「法定休日」として定められており、法定休日に対する割増率は1.35倍です。法定休日以外に企業が定めている休日は「法定外休日」といい、法定外休日に対する割増率は企業ごとに異なります。
深夜手当
深夜手当は、22時から翌朝5時までの労働に対して支払われる手当です。深夜手当の割増率は、1.25倍と定められています。医療・介護施設など夜勤が発生する職場では、「夜勤1回につき5,000円」といったように定額で支給される場合が多くなっています。
通勤手当
通勤手当は、通勤のためにかかる定期代やガソリン代に対して支払われる手当です。一般的に、経路が複数ある場合には最も安い経路が対象となることが多く、上限が設定されている場合も多々あります。
役職手当
役職手当は、特定の役職についている場合に支給される手当です。一般的に、役職が上がるほど、その額も高くなります。
住宅手当
住宅手当は、居住費の補助のために支払われる手当です。月々の家賃や住宅ローンの一部を補助することを目的に支給される場合が多く、その有無や支給額、支給条件などは企業によってさまざまです。
家族手当
家族手当は、扶養する家族がいる従業員に対して支払われる手当です。一般的に扶養人数に応じて支給額が増額されるものであり、「扶養手当」と呼ばれる場合もあります。
社会保険料
社会保険料は、けがや病気、失業などの不測の事態に備えて支払う保険料のことです。健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険の5つの保険があり、保険料は標準報酬月額や加入している健康保険組合によって異なります。標準報酬月額とは、社会保険料の計算簡略化のために、給与の平均月額をもとに分けられた等級のことです。基本給が上がり標準報酬月額の等級が上がれば、支払う保険料も高くなります。
所得税・住民税
所得税は所得額に応じて支払う税金であり、住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせた税金のことです。住民税は前年の所得に対して課税される「所得割(10%)」と、定額で課税される「均等割(5,000円)」で構成されていますが、自治体によって超過や減税が行われることがあります。また、所得が少ない場合には、均等割のみ、もしくは非課税となります。
各種積立金
企業によっては、独自の積立金制度が設けられている場合があります。主な積立金制度としては、財形貯蓄制度、従業員持株会制度などがあります。
欠勤控除
欠勤控除は、欠勤や遅刻・早退などで働かなかった時間分の賃金を給与から差し引くことを意味します。有給休暇などを使わずに休んだ場合などが該当し、「勤怠控除」と呼ばれることもあります。
まとめ
基本給は給与のベースとなる金額のことであり、そこに固定手当や変動手当を足し、社会保険料と税金を引いた額が手取り額となります。基本給の額は残業代やボーナスにも影響しますので、転職活動時などにはよく確認しておくようにしましょう。