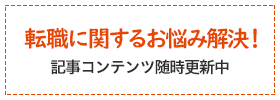選定療養とは?
選定療養は、健康保険の被保険者である患者さんが、特定の治療や医薬品の費用を追加で負担することで、保険適用の治療と保険適用外の治療を一緒に受けられるようにする制度です。
通常、保険適用の治療と保険適用外の治療は「混合診療」になるとして、同時に受けることが認められていません。しかし選定療養では、一部の治療や医薬品に関して、保険適用分は1~3割負担、保険適用外の部分に関しては全額負担することで、保険診療と同時に受けることが認められています。
選定療養の対象となる医療サービスや医薬品
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 小児う蝕の指導管理
- 180日以上の入院
- 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
などがあります。「予約診療」や「時間外診療」なども対象です。
選定療養制度によりこれらの医療サービスや治療を選択しやすくなることで、被保険者である患者さんは選択の幅を広げることができ、よりニーズに合った医療を受けられるようになるというメリットがあります。
プロフィールを見た事業所からスカウトが届く!
長期収載品の選定療養とは?
2024年10月1日に、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして「後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」がスタートしました。これは、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を患者さんが希望する場合、「特別の料金」の支払いが生じるという制度です。後発医薬品の活用を促すこと、それによる医療費負担の軽減、そして保険給付減少による医療保険財政の改善が、この制度の目的です。「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金と定められています。
長期収載品と後発医薬品の違い
長期収載品(先発医薬品)とは
長期収載品とは、同じ成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)が販売されている先発医薬品のことです。
先発医薬品とは
先発医薬品とは、最初に開発・承認・販売が行われた医薬品のことです。新薬とも呼びます。先発医薬品を開発した製薬メーカーには、20年~25年ほどの特許期間が与えられます。
後発医薬とは
後発医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に、ほかの製薬メーカーなどが同じ有効成分で作った医薬品のことです。ジェネリック医薬品とも呼ばれており、研究・開発費用がかからないため価格が安く設定されています。
選定療養の仕組み
後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養は、患者さんの希望により長期収載品の処方を行う場合が対象となります。
ただし、下記のような場合は選定療養の対象外です。
- 先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合
- 副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合
- 各学会などが作成しているガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推奨しているような場合
- 剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある場合
つまり、医師または薬剤師が「医療上の必要性がある」として先発医薬品の処方を行う場合は、「特別の料金」の負担が発生しません。また、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がないために長期収載品の処方を受けることになった場合も、「特別の料金」を負担する必要はありません。
プロフィールを見た事業所からスカウトが届く!
選定療養対象となる薬剤
選定療養の対象となる薬剤は、後発医薬品があり、その後発医薬品の薬価が長期収載品の薬価よりも低い薬剤です。加えて、後発医薬品が収載されてから5年が経過していること、もしくは後発品置換え率が 50%以上であることも、対象となる条件に含まれています。つまり、後発医薬品が収載されてから5年未満で、かつ置換え率が50%未満の薬剤は、選定療養の対象とはなりません。ただし、このような条件に当てはまる薬剤の数は少なく、ほぼすべての薬剤が選定療養の対象になります。
具体的には、解熱・鎮痛作用のあるブルフェン顆粒20%、消炎・鎮痛作用のあるロキソニン細粒10%、胃潰瘍や逆流性食道炎の治療に用いられるガスター錠10mgなどが選定療養の対象です。対象となる薬剤は制度開始時点で1096品目あり、厚生労働省のホームページで一覧が掲載されています。
計算方法
選定療養対象の長期収載品の処方を受ける場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の額を患者さんが負担することになります。
例えば、先発医薬品の薬価が100円、後発医薬品の薬価が60円だった場合、差額である40円の4分の1である「10円」が、通常の負担分とは別に支払う必要がある金額です。また、この10円は保険外のため課税対象となり、消費税分を加えて支払う必要があります。
「特別の料金」を除いた残りの費用に関しては、これまで通り保険給付の対象です。そのため、100円から10円を引いた90円に対して、1~3割の負担額を支払うこととなります。
注意点としては、端数処理などの関係で、「特別の料金」が4分の1ちょうどにはならない場合もあることです。また、後発医薬品が複数ある場合には、その中で最も高額な医薬品との価格差が用いられます。
Q&A
選定療養の長期収載品とは?
長期収載品とは、同じ有効成分で後発医薬品が販売されている先発医薬品のことです。
長期収載品選定療養の自己負担額はいくらですか?
選定療養の対象となる長期収載品の自己負担額は、自己負担割合によって異なります。3割負担の方の場合、後発医薬品との価格差の4分の1相当額が「特別の料金」となり、残りの4分の3の額のうち、3割が自己負担分となります。そのため、「特別の料金」に消費税をかけた額と、自己負担分を足した額が、長期収載品の自己負担額となります。


.png?fm=webp&fit=crop&w=305&h=163)