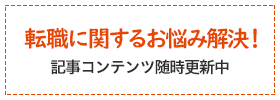属人化(ぞくじんか)の定義とその基本的な意味
今回取り上げるキーワードは「属人化」です。転職や離職が一般的になり、一つの組織にとどまらない人が増えた現代で、多くの組織を悩ませる問題です。
組織では、「属人化」が起こらないほうが安定性が高いとされます。なぜ、属人化は起きない方がよいのか、医療機関でも起こりやすい属人化の要因ともなる属人化について解説します。
属人化とは何か?
業務の手順や実態を特定の人物しか把握していない状態を、属人化といいます。詳細な業務内容を把握しているのが一人だけのため、その社員やスタッフが休職・退職をしてしまうと業務が滞ってしまったり、業務の質が低下してしまったりすることが、属人化の大きな問題です。現代の日本では、一つの企業にとどまらずに転職をすることが一般的になっており、そのような人材の流動化により、属人化が問題となる場面が増加しています。
属人化が起こる原因とは
属人化が起こる背景には、いくつかの原因があります。
リソース不足
一つ目は、業務量が多く、人的・時間的リソースが不足している場合です。このように業務過多に陥っている場合、業務の内容をほかのスタッフに教えたり、マニュアルを作成したりする時間が取れないために属人化するリスクが高くなります。
また、組織内に情報共有の仕組みがないことも、属人化の原因となります。業務内容を共有できるツールや場がない状態では、手間や工数をかけてまで業務共有をするのは困難です。情報共有による業務効率化や標準化に対し、適切な評価制度がないケースでも、情報共有をする価値が見いだせないために結果的に属人化に陥ってしまいます。
さらに、コロナ禍を経て導入する企業が増えているリモートワークに関しても、社員同士のコミュニケーションが不足したり、行っている仕事が見えづらくなったりし、情報共有が滞りやすくなります。
専門性が高い業務
そして、医療機関のように業務の難易度や専門性が高い場合にも、属人化のリスクは高くなります。業務遂行に一定レベル以上のスキルが必要になる場合には、特定のに業務が固定化されることが多く、業務内容の分担や教育が難しくなります。その結果「特定の社員がいないと業務が進まない」という状態に陥りやすくなってしまいます。
医療介護施設では、専門性とチームワークが求められるため、意識してマニュアル化するなど共有の仕組みづくりが大切です。
属人化と関連がある言葉とその関係性
「属人化」と似た言葉に、ブラックボックス化などがあります。
言葉の意味や属人化との違い、関係性を知っておくことで、属人化への理解をより深めることができます。
関連がある言葉を紹介します。
スペシャリスト
スペシャリストは、特定の分野において専門的な知識やスキルを持っている人のことを指します。専門性が高い業務を行っているという点で属人化に共通する部分はありますが、その知識やスキルが共有・可視化されている場合も多く、必ずしも属人化につながるというわけではありません。属人化を避けつつ、スペシャリストの専門性を活かすためには、知識共有や業務フローの整備が重要です。
ブラックボックス化
ブラックボックス化とは、業務の流れや内容が周囲からはわからない状態を指し、属人化によって起こるリスクです。もともとはプログラミングの世界で使われていた言葉ですが、近年ではそのほかの場面でも広く使われるようになっており、「業務内容やプロセスが不透明な状態」をブラックボックス化という言葉で表すことが多くなっています。
暗黙知
暗黙知とは、経験や勘などに基づく知識のことであり、ノウハウやコツと言い換えることもできます。暗黙知は感覚に頼っている部分が大きいことから言語化や周囲への説明が難しく、属人化するリスクが大きいという問題をはらんでいます。暗黙知による属人化を避けるためには、関係者間での認識のずれの解消や言葉の定義づけが必要になります。
業務における属人化のリスクとは?
属人化は、ビジネス上のさまざまな問題を引き起こすリスクがあります。属人化による代表的なリスクを4つ解説します。
業務の停滞と質が低下する
属人化することで起こる代表的なリスクとして挙げられるのが、業務の停滞と質の低下です。特定の個人に業務を依存していることで、そのがスタッフが休んだり退職してしまったりすると、業務が進まなくなったり、それまでの質を維持できなくなったりするリスクがあります。特に、前述した「暗黙知」で行っていた業務がある場合は、その影響は甚大です。
マニュアルや手順書があり、かろうじて業務が進められる場合でも、それまでよりも長い時間がかかったり、人手が多く必要になったりと、業務の効率に大きな影響を与えます。
退職でナレッジ・ノウハウが消失する
属人化している状態では、業務に係るナレッジやノウハウが特定の個人にのみ蓄積されています。そのため、ほかの社員への引継ぎが不十分な状態でその社員が退職や転職をしてしまうと、組織はそのナレッジ・ノウハウを失うことになります。競合他社に転職した場合には、知識やスキルの流出を招くことになり、企業の競争力にも影響を与えることになります。
マネジメント・人事評価が困難になる
特定の業務を個人が行っていて周囲がその内容やプロセスを把握できない状況では、その業務内容や進め方が適切なのかどうかの判断が困難になります。それにより、組織の管理者による進捗管理や必要なタイミングでのフォロー、人員配置といったマネジメントが難しくなるというリスクがあります。また、そのような状態では適切に人事評価を下すこともできません。
特定の従業員への負担の増加
属人化のリスクは、その担当者に対しても生じます。業務が偏っていることによる精神的な負担、業務量が多いことによる体力的・精神的負担、業務内容を理解してもらえないなど周囲とのコミュニケーションが難しくなることによる精神的な負担など、その負担の内容はさまざまです。
そういったことが原因で退職につながってしまえば、先に挙げたような業務の停滞や質の低下、ノウハウやナレッジの流出につながることになります。
属人化の防止と解消方法、対策
属人化を防止・解消するためには、まずは属人化によりブラックボックス化している業務の洗い出しをする必要があります。担当者や関係部署などにも話を聞き、業務の詳細な内容と課題をリストアップしましょう。
業務の標準化と可視化
業務の洗い出しをした後は、その業務の標準化を進めます。業務の標準化とは、業務プロセスの整備やマニュアル作成などによって、その業務を誰もが進められるようにすることです。具体的な方法としてはマニュアルの作成やツール導入での簡略化・自動化、チェックリストの導入などがあります。マニュアルを作成する際には、図解やトラブル事例を含めるなど、その業務を初めて行う社員でもわかりやすくすることが大切です。
ナレッジシェアリングの推進
ナレッジシェアリングとは、知識やスキルを共有できる場を作ることです。ナレッジ共有ツールを活用したり、定期的に業務共有の場を設けたりすることで、業務にはどのような課題があるのかが把握できるようにしましょう。そういった共有の仕組みを設けることは、属人化を防ぐだけでなく、自分が担当している業務の改自分以外の社員がどのような業務をどのように行っているのか、その善方法や課題に気付くきっかけにもなります。
【マニュアル化のポイント】新規スタッフに質問されたことをメモしておき、項目ごとにマニュアル化して簡易的に作る方法もあります。医療機関などでは、マニュアル制作に手が回らないことも多いため、教育の時間を使って随時更新するかたちで共有すると手間が省けます。
定期的な見直しと継続的なモニタリング
属人化を解消するためには、一度仕組みを構築した後も継続してその取り組みを続けていくことが大切です。定期的にマニュアルを見直したり、担当者に話を聞いたりするなどして、新たな課題が出てきてはいないか、再度ブラックボックス化している業務はないかを確認するようにしましょう。属人化の解消が難しい場合などは、担当者を複数名にしてチーム制にしたり、業務をアウトソーシングしたりと、別の視点から解消方法を模索することが求められます。
属人化を防いで持続可能な職場に
属人化は、業務が特定の個人に偏り、ブラックボックス化している状態を指します。属人化している状態はモチベーションの向上や業務の効率性アップにつながるというメリットがある一方で、会社全体の生産性やマネジメント効率が低下したり、その社員がいなくなることで業務の停滞や質の低下につながったりするというリスクがあります。そういった状態を避けるためには、業務の標準化・可視化のための仕組みづくりと、その後の継続的な見直し・モニタリングが必要です。属人化解消を進めることで、人材不足や人材流出にも負けない持続可能なビジネスを展開していきましょう。
医療・介護職の採用をお考えの方はこちら
採用ご担当者の方はこちら



.png?fm=webp&fit=crop&w=305&h=163)